2010年05月05日
パーソナライズ
e-Govにおけるユーザー登録みたいなもんです。
以前の電子申請システムのページには一番下にあったんで目立たなかったんですが、
今度からは前に出てきました。

パスワードだけでなくパーソナライズIDも自由に選べるので、新規登録ボタンを押す前にどういうIDにするか考えておくといいでしょう。
IDは英数字のみ、パスワードは記号も使えます。
申請する手続きについて検索したり、申請後に到達番号が交付されたときにパーソナライズ登録ボタンが表示されます。
手続詳細一覧 よく使う申請手続を登録しておくことができます。
申請案件一覧 到達番号を記録しておいて進捗状況が確認できます。
単発で電子申請する場合なら登録しなくてもいいことですが、やはり社労士のように繰り返し申請する者にとっては便利な機能です。
なお、終わったときは必ず右上の閉じるボタンを押すことをお忘れなく。
さもないと次回ログインしたときにこういう警告文が表示されます。

まぁ再度パスワードを入力することで再ログインできるんですけどね。
私もしょっちゅうこれやってしまいます。
以前の電子申請システムのページには一番下にあったんで目立たなかったんですが、
今度からは前に出てきました。
パスワードだけでなくパーソナライズIDも自由に選べるので、新規登録ボタンを押す前にどういうIDにするか考えておくといいでしょう。
IDは英数字のみ、パスワードは記号も使えます。
申請する手続きについて検索したり、申請後に到達番号が交付されたときにパーソナライズ登録ボタンが表示されます。
手続詳細一覧 よく使う申請手続を登録しておくことができます。
申請案件一覧 到達番号を記録しておいて進捗状況が確認できます。
単発で電子申請する場合なら登録しなくてもいいことですが、やはり社労士のように繰り返し申請する者にとっては便利な機能です。
なお、終わったときは必ず右上の閉じるボタンを押すことをお忘れなく。
さもないと次回ログインしたときにこういう警告文が表示されます。

まぁ再度パスワードを入力することで再ログインできるんですけどね。
私もしょっちゅうこれやってしまいます。
2010年04月27日
新しくなったe-Gov
イーガブが新しくなりました。
・・・と言ってもリニューアルは3月28日だったそうですが。
こんなロゴだったのが → こんなのになった!


今までのに慣れてると少々戸惑います。
しかし操作性はかなりよくなっておりますので、前より楽に電子申請ができます。
特に変わったところは申請前の届書を預かってもらえるようになったこと。
今まで書類とその構成情報を一々選択して送信していたのに比べ、ずっと簡単になりました。
発行された預かり票を使って申請すれば、送るべき書類の管理が楽々です。
・・・と言ってもリニューアルは3月28日だったそうですが。
こんなロゴだったのが → こんなのになった!


今までのに慣れてると少々戸惑います。
しかし操作性はかなりよくなっておりますので、前より楽に電子申請ができます。
特に変わったところは申請前の届書を預かってもらえるようになったこと。
今まで書類とその構成情報を一々選択して送信していたのに比べ、ずっと簡単になりました。
発行された預かり票を使って申請すれば、送るべき書類の管理が楽々です。
2010年02月15日
電子申請フェア
2月10日、名古屋で行われた電子申請フェアに行ってきました。
さて、これをきっかけに電子申請普及するでしょうか?
e-Govの仕様公開によって、ソフト開発が進み、簡単にはなりそうです。
6月にはzipファイルにまとめて一括申請も出来るようになるとのことですし・・・
でも、まだまだ委任状をJPEGにするとか、JAVAとかわからない人も多いでしょうし、
あまり簡単になっちゃうのもセキュリティ上どうなのか???
何れにしても政府が提供する無料の申請環境じゃ行き詰るようになってしまうのか?
有料ソフトを買うならどれがいいのか???
悩みはつきませんね。
さて、これをきっかけに電子申請普及するでしょうか?
e-Govの仕様公開によって、ソフト開発が進み、簡単にはなりそうです。
6月にはzipファイルにまとめて一括申請も出来るようになるとのことですし・・・
でも、まだまだ委任状をJPEGにするとか、JAVAとかわからない人も多いでしょうし、
あまり簡単になっちゃうのもセキュリティ上どうなのか???
何れにしても政府が提供する無料の申請環境じゃ行き詰るようになってしまうのか?
有料ソフトを買うならどれがいいのか???
悩みはつきませんね。
2009年12月11日
e-Gov 謎のエラーとは???
電子申請しようと思ったけど、こんなエラーが出て止めてしまった方はいませんか?

「原因が不特定」・・・って、どういうこと???
こんな表示が出るとどうしていいのかわかんないですよね。
面倒だ! 電子申請なんかやめちゃえ。
そう思うのも無理はありません。
実際私も断念しかけましたから・・・
しかし、こちとら元電子化委員ですからね。ちょっとそれじゃ済まされない意地ってもんがあります。
そして気づきました。これが原因です。JAVA6.0のコントロールパネルをご覧ください。

この「Java Plug-in」という設定から「次世代のJava Plug-inを有効にする(ブラウザの再起動が必要)」のチェックを外せばよかったのです。
よく読むとJava実行環境の設定変更についての解説ページがあるのですが、先ほどのエラーからこれが原因だと気付く方は滅多にいないのではないでしょうか?
いや、きっとそこまでの知識ある人なら、JAVA6.0インストールしてすぐにチェック外すんだろうな。
これでもう大丈夫。もう一度電子申請にチャレンジしてみてください。

「原因が不特定」・・・って、どういうこと???
こんな表示が出るとどうしていいのかわかんないですよね。
面倒だ! 電子申請なんかやめちゃえ。

そう思うのも無理はありません。
実際私も断念しかけましたから・・・
しかし、こちとら元電子化委員ですからね。ちょっとそれじゃ済まされない意地ってもんがあります。
そして気づきました。これが原因です。JAVA6.0のコントロールパネルをご覧ください。

この「Java Plug-in」という設定から「次世代のJava Plug-inを有効にする(ブラウザの再起動が必要)」のチェックを外せばよかったのです。
よく読むとJava実行環境の設定変更についての解説ページがあるのですが、先ほどのエラーからこれが原因だと気付く方は滅多にいないのではないでしょうか?
いや、きっとそこまでの知識ある人なら、JAVA6.0インストールしてすぐにチェック外すんだろうな。
これでもう大丈夫。もう一度電子申請にチャレンジしてみてください。
2009年11月05日
助成金セミナーのお知らせ
静岡社労士会初の試みとなるであろう、ウェブサイト上でのセミナー告知。
専用ページを設けて、参加申込がネットで出来るようになりました。
しかし便利になっても、見てくれる人がいなきゃ話になりません。
そこで今回はバナー広告も作ってもらいました。
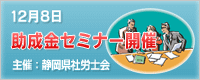
これをクリックすると助成金セミナーのページが表示されるわけですね。

少し小さいサイズのものも作って頂きました。
このバナー広告を貼ってくれるブロガー社労士さん、もちろんそれ以外のブロガーさんでも歓迎いたします。
よろしくお願いいたします。
専用ページを設けて、参加申込がネットで出来るようになりました。
しかし便利になっても、見てくれる人がいなきゃ話になりません。
そこで今回はバナー広告も作ってもらいました。
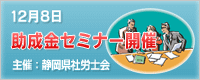
これをクリックすると助成金セミナーのページが表示されるわけですね。

少し小さいサイズのものも作って頂きました。
このバナー広告を貼ってくれるブロガー社労士さん、もちろんそれ以外のブロガーさんでも歓迎いたします。
よろしくお願いいたします。
2009年09月06日
県会ページ リニューアル
 この週末、県会ホームページを新しいものに入れ替えました。
この週末、県会ホームページを新しいものに入れ替えました。ページデザインは業者に委託したものですから、見た目が綺麗です。
でも、まだまだこれからです。
旧ページもそのままの形で残してありますが、少しずつ新ページのデザインに合わせてリンク替えすることになるでしょう。
会員ページももっと便利に使えるよう、PDF書類のダウンロードページを設ける予定です。
ご意見等お聞かせください。
2009年07月01日
ファイル転送
 広報委員になって早々HPの書き換え作業をやりました。
広報委員になって早々HPの書き換え作業をやりました。県会事務局からFTPアカウント=HPの置かれたサーバーに接続するためのID・パスワードを教えてもらったわけで責任重大です。
通常HPアドレスの前についてるのはHTTP、これをFTPに変えるとどうなるのか?
HTTPは片道だけど、FTPは往復が可能なネット接続法なわけでして、
これを使うのは緊張します。うっかり間違うと大事なデータを消してしまいかねないですから。
インターネットエクスプローラでもFTPが使えますが、単なるエクスプローラでも見ることができ、これだと自分のパソコン内のフォルダを開くのと変わりません。
ただし接続前にIDとパスワードを入力する画面が出るわけですが…
FTPソフトというものもあります。これは自分のパソコンに作ったHPデータとFTP接続したネット上のデータを左右に並べて、同期をとるという仕組みです。
これだと自分のパソコンに同じデータのバックアップがあるわけですから、失敗を恐れなくていいですよね。
2009年06月06日
今年度からは広報委員でHP担当
さて、たまにしか更新しないこのブログですが、
そうしているうち電子化委員の任を解かれました。
 しかし、今度は広報としてHP担当になってしまいましたので、
しかし、今度は広報としてHP担当になってしまいましたので、
タイトルの「電子化大作戦」がより広い意味になったとも言えます。
静岡県社労士会のHPにも今後ブログ形式のページを設ける予定がありますので、
このはまぞうで勉強してきたことが役に立つときがくるかもしれないです。
そうしているうち電子化委員の任を解かれました。
 しかし、今度は広報としてHP担当になってしまいましたので、
しかし、今度は広報としてHP担当になってしまいましたので、タイトルの「電子化大作戦」がより広い意味になったとも言えます。
静岡県社労士会のHPにも今後ブログ形式のページを設ける予定がありますので、
このはまぞうで勉強してきたことが役に立つときがくるかもしれないです。
タグ :広報委員
2009年04月01日
Vista対応!
社会保険庁が提供しているプログラムがようやくWindows Vista対応になりました。
 磁気媒体届書作成プログラムの最新版はVer5.10です。
磁気媒体届書作成プログラムの最新版はVer5.10です。
Vista対応になったという以外、特に変更点はありません。もちろんXPでも使えます。
被扶養者変更届にも対応するようになるかなぁ~と思っていたんですが、まだのようですね。
これで社労士の電子申請もより増えてくるかなぁ。
 磁気媒体届書作成プログラムの最新版はVer5.10です。
磁気媒体届書作成プログラムの最新版はVer5.10です。Vista対応になったという以外、特に変更点はありません。もちろんXPでも使えます。
被扶養者変更届にも対応するようになるかなぁ~と思っていたんですが、まだのようですね。
これで社労士の電子申請もより増えてくるかなぁ。
2009年02月18日
出張サポートと新人研修
最近まめにこのブログを更新するようになったわけは、
今月と来月、電子化委員として喋ることが続くからだ。
出張サポートは社労士事務所への個別訪問、新人研修は県会へ出向くことになっている。
労務に関する研修ならば、社労士なら当然周知しているであろうという話はする必要がない。
だが電子申請については、パソコンの知識。どのレベルから話をしていいのかがわからない。
よってこれまでの研修では必ず、ついてけね~よって顔した人を見かけたものだ。
 今回初めて個別訪問によって実際その事務所で使っているパソコンを操作しながら説明する。
今回初めて個別訪問によって実際その事務所で使っているパソコンを操作しながら説明する。
まるで家庭教師みたいだね。
しかし人様のパソコンというのは、それぞれ使い勝手が違う。
自分とこのパソコンでできたことが同じようにできるとは限らない。
最初に訪問した社労士事務所では、スキャナの使い方がわからないままだったし、e-Govでの手順も原因不明のエラーによって幾度も中段された。
不完全なサポートのままで終わってしまったことが悔やまれる。
今月と来月、電子化委員として喋ることが続くからだ。
出張サポートは社労士事務所への個別訪問、新人研修は県会へ出向くことになっている。
労務に関する研修ならば、社労士なら当然周知しているであろうという話はする必要がない。
だが電子申請については、パソコンの知識。どのレベルから話をしていいのかがわからない。
よってこれまでの研修では必ず、ついてけね~よって顔した人を見かけたものだ。
まるで家庭教師みたいだね。
しかし人様のパソコンというのは、それぞれ使い勝手が違う。
自分とこのパソコンでできたことが同じようにできるとは限らない。
最初に訪問した社労士事務所では、スキャナの使い方がわからないままだったし、e-Govでの手順も原因不明のエラーによって幾度も中段された。
不完全なサポートのままで終わってしまったことが悔やまれる。
2009年02月08日
昔はディスクだった
 こんなものが出てきました。
こんなものが出てきました。そうそう、電子申請が始まる前にはこうやってCD-ROMで磁気媒体届書作成プログラム配布されていたんですね。
いまじゃダウンロードが当たり前ですが、当時はまだネット接続されてなかったり、ダイヤル回線が遅かったりして、この方法で普及させるしかなかったわけです。
今やブロードバンドが普及して、容量の大きなプログラムでも数秒でダウンロードが可能になりました。
そういえば昨今じゃCDを使うことってずいぶん減ってる気がします。
プログラム自体も頻繁にアップデートして最新版にしておかないと、安心できない時代になりました。
市販ソフトでさえCDからインストールすると同時に最新版にアップデートするようなこともしょっちゅうです。
ウィルスソフトに至っては毎日がアップデートの繰り返し。
再インストールするときのためにインストール用CDを保管しておいたものですが、これはもう使えないなぁ。
 ちなみに最新の磁気媒体届書作成プログラムはバージョン5.00です。
ちなみに最新の磁気媒体届書作成プログラムはバージョン5.00です。 2009年02月07日
スキャナ
代理送信による電子申請について、最大の難関となりそうなのが委託証明書の画像データ作成である。
この仕様について疑問点が多々あることは以前の記事に書いたのだが、それでも今はこのやり方でやるしかない。
書類読み取り装置として広く使われているものがスキャナである。
コピー機の原稿読み取り部分が独立したものだと思えばわかりやすい。
あるいは複合機という名でコピー・FAX・プリンタ・スキャナの用途を一台で賄う物もあるし、複数の原稿を連続して両面スキャンできるというペーパーレス化に特化した製品も出ている。
いずれのものであろうとA4用紙が使えればいい。だが問題は解像度とファイル形式にある。
解像度は1インチに幾つの点を割り当てるか、ドットパーインチを略してdpiという単位を使う。
通常印刷用やOCR(文字認識)用は300~500dpiの解像度でスキャンしているが、これはファイルサイズが大きい。
社会保険の電子申請用ではJPEGで300KBまでという決まりになっているから、そのサイズにするためには150dpiぐらいに設定してスキャンする必要がある。
そしてもう一つ設定に気をつけるのがファイル形式。JPEGというのは写真データである。
実は業務用スキャナの付属ソフトには、この形式をサポートしていないことが多い。
FAX用のTIFか電子マニュアルに多く利用されるPDF形式で取り込むものが殆どだろう。
雇用保険の電子申請はPDFでいいのだが、なぜか社会保険はJPEG?
画像加工できるソフトで形式変換するか、あるいは家庭用のスキャナを使うか、いっそスキャナを使わずデジカメで写真を撮ってしまうか・・・
この仕様について疑問点が多々あることは以前の記事に書いたのだが、それでも今はこのやり方でやるしかない。
書類読み取り装置として広く使われているものがスキャナである。

コピー機の原稿読み取り部分が独立したものだと思えばわかりやすい。
あるいは複合機という名でコピー・FAX・プリンタ・スキャナの用途を一台で賄う物もあるし、複数の原稿を連続して両面スキャンできるというペーパーレス化に特化した製品も出ている。
いずれのものであろうとA4用紙が使えればいい。だが問題は解像度とファイル形式にある。
解像度は1インチに幾つの点を割り当てるか、ドットパーインチを略してdpiという単位を使う。
通常印刷用やOCR(文字認識)用は300~500dpiの解像度でスキャンしているが、これはファイルサイズが大きい。
社会保険の電子申請用ではJPEGで300KBまでという決まりになっているから、そのサイズにするためには150dpiぐらいに設定してスキャンする必要がある。
そしてもう一つ設定に気をつけるのがファイル形式。JPEGというのは写真データである。
実は業務用スキャナの付属ソフトには、この形式をサポートしていないことが多い。
FAX用のTIFか電子マニュアルに多く利用されるPDF形式で取り込むものが殆どだろう。
雇用保険の電子申請はPDFでいいのだが、なぜか社会保険はJPEG?
画像加工できるソフトで形式変換するか、あるいは家庭用のスキャナを使うか、いっそスキャナを使わずデジカメで写真を撮ってしまうか・・・
2009年02月03日
「窓口一郎」になってみよう!
電子申請をするためには電子証明書が必要ですが、持っていますか?
e-Govには電子申請体験システムというページがあって、社労士はもちろん社労士でない人も電子申請を体験してみることができます。
この体験版で使われる電子証明書の人物が窓口一郎という架空の人物なのです。
試しに窓口一郎の電子証明書をダウンロードしてみてください。
証明書をダブルクリックしてインポートします。パスワードはそのまんま「password」。詳しい手順はこちらです。
 インポートできたら、インターネットエクスプローラのメニューにあるツール→インターネットオプション→コンテンツ→証明書→個人とクリックしてたどり、「Ichiro Madoguchi」という証明書があるのを確認してみてください。
インポートできたら、インターネットエクスプローラのメニューにあるツール→インターネットオプション→コンテンツ→証明書→個人とクリックしてたどり、「Ichiro Madoguchi」という証明書があるのを確認してみてください。
サブジェクトの別名を見るとこの男を証明書は「模擬民間認証局」から発行されています。
なかなか怪しいヤツだな。窓口一郎め!(笑)
もちろんホンモノの証明書はこの部分に信頼できるところの名称が出てきます。
ちなみにこちらは私の証明書
ちゃんと社労士連合会から証明されています。
e-Govには電子申請体験システムというページがあって、社労士はもちろん社労士でない人も電子申請を体験してみることができます。
この体験版で使われる電子証明書の人物が窓口一郎という架空の人物なのです。
試しに窓口一郎の電子証明書をダウンロードしてみてください。
証明書をダブルクリックしてインポートします。パスワードはそのまんま「password」。詳しい手順はこちらです。
 インポートできたら、インターネットエクスプローラのメニューにあるツール→インターネットオプション→コンテンツ→証明書→個人とクリックしてたどり、「Ichiro Madoguchi」という証明書があるのを確認してみてください。
インポートできたら、インターネットエクスプローラのメニューにあるツール→インターネットオプション→コンテンツ→証明書→個人とクリックしてたどり、「Ichiro Madoguchi」という証明書があるのを確認してみてください。サブジェクトの別名を見るとこの男を証明書は「模擬民間認証局」から発行されています。
なかなか怪しいヤツだな。窓口一郎め!(笑)
もちろんホンモノの証明書はこの部分に信頼できるところの名称が出てきます。
ちなみにこちらは私の証明書
ちゃんと社労士連合会から証明されています。
2008年11月23日
協会けんぽの電子申請
 実は電子化委員長から言われるまで気づかずにいたのですが、今年10月から分割民営化された全国健康保険協会にも電子申請システムがあるのです。
実は電子化委員長から言われるまで気づかずにいたのですが、今年10月から分割民営化された全国健康保険協会にも電子申請システムがあるのです。へぇ~あったんだ!
・・・よく見ると電子申請は情報提供サービスの中の一部なんですね。
電子申請以外にも健康診断の申し込みや医療費の照会などのサービスがあります。
利用登録するとIDパスワードが発行され、それは郵送で届くそうなので利用まで少し日にちがかかります。
でも現在社労士が代理で出来るのは保険証や高齢受給者証の再交付申請だけですけどね。
それだって省略できるのは事業主の電子署名だけで被保険者の署名は必要になるから、まだまだ実用にはならないところだと思います。そうやたら保険証なくす人が出てくるわけじゃないし。
2008年11月10日
しばらくぶりです
気がつけば長い事更新を怠っておりました。
思えば算定基礎届の時期直前になって、IDパスワードがいらない「代理送信」なんてのが出てきてしまって、せっかく行った電子化研修も半分くらい無意味になってしまったので、ちょっとやる気が失せておりました。
おかげで今年の算定基礎届、電子申請でやってみたという話を聞きません。
ホントにタイミングが悪かった。もうちょい早いか遅いかしてたら、違う展開になっていたかも。
そんなわけで、私もここしばらく電子申請のための委任状には手をつけていませんが、
算定に関しては1件だけ代理送信で手続きしています。
忘れないうちに、その手順や感じたことなどをここに記録しておこうと思っております。
思えば算定基礎届の時期直前になって、IDパスワードがいらない「代理送信」なんてのが出てきてしまって、せっかく行った電子化研修も半分くらい無意味になってしまったので、ちょっとやる気が失せておりました。
おかげで今年の算定基礎届、電子申請でやってみたという話を聞きません。
ホントにタイミングが悪かった。もうちょい早いか遅いかしてたら、違う展開になっていたかも。
そんなわけで、私もここしばらく電子申請のための委任状には手をつけていませんが、
算定に関しては1件だけ代理送信で手続きしています。
忘れないうちに、その手順や感じたことなどをここに記録しておこうと思っております。
2008年06月29日
「代理送信」始まる
詳細がハッキリするまで、更新が滞ってたこのブログ。
ようやく事の次第が明らかになったので、久々の記事投稿である。
新しい電子申請の方法は「代理送信」という。
ID・パスワードは事業主の電子証明書の代わりに必要なものであったが、
とうとう社労士が手続きを代理するのだから、事業主の署名はいらなくなったのだ。
・・・委託証明書を画像データにして添付することが条件。
社会保険はJPEG、雇用保険はPDF形式にして、いずれも300KBまで。
なんじゃあ、そりゃぁ?!
そもそも社労士は社会保険事務所に委託先を届け出ているハズ。
それを毎回添付しろってのは、意味あるんだろうか?
JPEGの300KBってのはかなり画質が低い。なのに鮮明な画像を要求しているようだ。
しかも社会保険と雇用保険で保存形式が違うものを用意するってのも何故なんだ?
たぶん「ウチにはスキャナなんてないぞ!」という社労士がかなりいるだろう。
デジカメでもいいというなら、むしろカメラ付携帯のほうが便利じゃないかな。
デジカメで300KB以下の写真を撮るのは難しいよね。
ようやく事の次第が明らかになったので、久々の記事投稿である。
新しい電子申請の方法は「代理送信」という。
ID・パスワードは事業主の電子証明書の代わりに必要なものであったが、
とうとう社労士が手続きを代理するのだから、事業主の署名はいらなくなったのだ。
・・・委託証明書を画像データにして添付することが条件。
社会保険はJPEG、雇用保険はPDF形式にして、いずれも300KBまで。
なんじゃあ、そりゃぁ?!
そもそも社労士は社会保険事務所に委託先を届け出ているハズ。
それを毎回添付しろってのは、意味あるんだろうか?
JPEGの300KBってのはかなり画質が低い。なのに鮮明な画像を要求しているようだ。
しかも社会保険と雇用保険で保存形式が違うものを用意するってのも何故なんだ?
たぶん「ウチにはスキャナなんてないぞ!」という社労士がかなりいるだろう。
デジカメでもいいというなら、むしろカメラ付携帯のほうが便利じゃないかな。
デジカメで300KB以下の写真を撮るのは難しいよね。
2008年05月25日
まだ詳細は不明ですが・・・
2008年05月02日
これまでのあらすじ・その2
前回説明した磁気媒体届を踏まえて、電子申請が可能になるといってもいいだろう。
要は入れ物と送り方が替わっただけだ。
窓口持参か郵送していたフロッピーから、中身のCSVファイルをインターネットで送信する。
そう考えれば大きな変化ではない。実際社労士と事業主、届け先役所の関係が変わったわけではないのだ。
だが、電子化に伴いパソコンを使った作業が徐々に増えていく事になっていく。
磁気媒体届書作成プログラムに続き、届出プログラムが厚労省より提供された。
文字通りファイル送信のためのソフトだ。
印鑑の代わりに電子証明書を使い、CSVファイルに社労士と事業主が署名し、役所へ送信する。
さてこの電子申請、開始早々はなかなか普及しなかった。
その理由として大きなハードルとなっていたのは、事業主の電子証明書が必要な点だ。
費用もかかるし、社労士としてはなかなか事業主さんに頼み難い。
そこで社労士が手続きする場合に限り、事業主の電子証明書の代わりにID・パスワードを使えるようになった。
これは包括委任状方式と呼ばれ、社労士と事業主との間で委任状を取り交わした場合にID・パスワードが発行された。
これを電子証明書の代わりに付けるのだが、そのまま付けてもダメだ。
暗証番号暗号化プログラムというもので更に暗号化して電子データに付けることで署名が完了する。
なぜこのような面倒くさいことをしなくてはいけないのか?
理由は明らかにされていないが、こう推測できる。
つまり、電子証明書なら認証局で管理されているのでその都度確認ができる。ちゃんとした身分証だ。
しかし、ID・パスワードはせいぜい“合言葉”程度のものだ。ここが有料と無料の違いなんだろうな。
そこで毎度合言葉を変更するなら、この方法を認めようってことなんじゃないだろうか。

さて、これで事業主の電子証明は省略されたが結果的にまた社労士の仕事が増えた。
事前に事業主と委任状を交し、保険番号等をデータ化して県社労士会へ送付。
県会から社会保険事務局へID・パスワード発行の申請。事業主宛に送付されたID・パスワード通知を回収して管理する。
それを行ったうえで、毎回それを暗号化して電子データに貼り付けねばならなくなったのだ。
包括委任状作成プログラム・暗号化プログラム・磁気媒体届書作成プログラム・届出プログラムとパソコンで行う仕事も4つに増えた。
これって、もうちょっとシンプルにならないものだろうか?
次回へ続く・・・。
要は入れ物と送り方が替わっただけだ。
窓口持参か郵送していたフロッピーから、中身のCSVファイルをインターネットで送信する。
そう考えれば大きな変化ではない。実際社労士と事業主、届け先役所の関係が変わったわけではないのだ。
だが、電子化に伴いパソコンを使った作業が徐々に増えていく事になっていく。
磁気媒体届書作成プログラムに続き、届出プログラムが厚労省より提供された。
文字通りファイル送信のためのソフトだ。
印鑑の代わりに電子証明書を使い、CSVファイルに社労士と事業主が署名し、役所へ送信する。
さてこの電子申請、開始早々はなかなか普及しなかった。
その理由として大きなハードルとなっていたのは、事業主の電子証明書が必要な点だ。
費用もかかるし、社労士としてはなかなか事業主さんに頼み難い。
そこで社労士が手続きする場合に限り、事業主の電子証明書の代わりにID・パスワードを使えるようになった。
これは包括委任状方式と呼ばれ、社労士と事業主との間で委任状を取り交わした場合にID・パスワードが発行された。
これを電子証明書の代わりに付けるのだが、そのまま付けてもダメだ。
暗証番号暗号化プログラムというもので更に暗号化して電子データに付けることで署名が完了する。
なぜこのような面倒くさいことをしなくてはいけないのか?
理由は明らかにされていないが、こう推測できる。
つまり、電子証明書なら認証局で管理されているのでその都度確認ができる。ちゃんとした身分証だ。
しかし、ID・パスワードはせいぜい“合言葉”程度のものだ。ここが有料と無料の違いなんだろうな。
そこで毎度合言葉を変更するなら、この方法を認めようってことなんじゃないだろうか。

さて、これで事業主の電子証明は省略されたが結果的にまた社労士の仕事が増えた。
事前に事業主と委任状を交し、保険番号等をデータ化して県社労士会へ送付。
県会から社会保険事務局へID・パスワード発行の申請。事業主宛に送付されたID・パスワード通知を回収して管理する。
それを行ったうえで、毎回それを暗号化して電子データに貼り付けねばならなくなったのだ。
包括委任状作成プログラム・暗号化プログラム・磁気媒体届書作成プログラム・届出プログラムとパソコンで行う仕事も4つに増えた。
これって、もうちょっとシンプルにならないものだろうか?
次回へ続く・・・。
2008年04月24日
JAVA
あらすじの途中だが、ちょっと解説の補足。
 電子申請でデータのやりとりを影で行っているプログラムがJAVAである。
電子申請でデータのやりとりを影で行っているプログラムがJAVAである。
実はパソコンを買った時からインストールされていて知らずに使っていることが殆どだ。
もっと正確にいうとJAVAはプログラミング言語である。JAVA言語で書かれたプログラムが内部で動いているということだ。
JAVAは役者に芝居をつける演出家であり、人間の書いた台本を機械の言葉に訳す翻訳家でもあると思えばわかりやすいかな。
パソコンに限らず、携帯電話でも様々な機能にJAVAが使われていたりする。
目立たない存在だけど、実は我々の生活に欠かせないものだったりするんだなぁ。
しかし、電子申請を行うためにはJAVAの存在を知らずに済ますことはできない。
機密書類を扱わせるからには、盗まれたり擦り返られたりしてはならないからだ。
プログラムに弱点が見つかった時はすぐに公表される。脆弱性という言い方をする。
そしてすぐその弱点を克服した新バージョンが開発され、公開される。
そう、だから常にアップデートして強いプログラムにしておけばいいのだが、そうばかりでもない。
電子申請を扱う役所(特にe-Gov)が新バージョンに対応できなくしまうことが起きてくるからだ。
結果、XPなら1.4.2か5.0、Vistaなら6.0という具合に使えるバージョンが決められてしまう。
普段意識してなかったJAVAだけに、これを確認するのは難しいかも。
そこで今一番簡単は確認方法はe-Gov電子申請システムの動作環境についてというページ。
ここの確認するボタンを押して判断してもらうのが確実だ。
「推奨のブラウザ…推奨の実行環境が検出されました」と表示されればOK!
あるいは今この記事を見ているインターネットエクスプローラのメニューにある「ツール」から「SunのJAVAコンソール」をクリックしてもいい。バージョン番号が確認できる。(但し5.0は1.5.…、6.0は1.6.…と表示される。)
バージョンが合わない場合はe-Govの解説にしたがって使用可能なJAVAのインストールを!
途中英語のサイトになっちゃうけど、がんばってプログラムダウンロードしてね。
 電子申請でデータのやりとりを影で行っているプログラムがJAVAである。
電子申請でデータのやりとりを影で行っているプログラムがJAVAである。実はパソコンを買った時からインストールされていて知らずに使っていることが殆どだ。
もっと正確にいうとJAVAはプログラミング言語である。JAVA言語で書かれたプログラムが内部で動いているということだ。
JAVAは役者に芝居をつける演出家であり、人間の書いた台本を機械の言葉に訳す翻訳家でもあると思えばわかりやすいかな。
パソコンに限らず、携帯電話でも様々な機能にJAVAが使われていたりする。
目立たない存在だけど、実は我々の生活に欠かせないものだったりするんだなぁ。
しかし、電子申請を行うためにはJAVAの存在を知らずに済ますことはできない。
機密書類を扱わせるからには、盗まれたり擦り返られたりしてはならないからだ。
プログラムに弱点が見つかった時はすぐに公表される。脆弱性という言い方をする。
そしてすぐその弱点を克服した新バージョンが開発され、公開される。
そう、だから常にアップデートして強いプログラムにしておけばいいのだが、そうばかりでもない。
電子申請を扱う役所(特にe-Gov)が新バージョンに対応できなくしまうことが起きてくるからだ。
結果、XPなら1.4.2か5.0、Vistaなら6.0という具合に使えるバージョンが決められてしまう。
普段意識してなかったJAVAだけに、これを確認するのは難しいかも。
そこで今一番簡単は確認方法はe-Gov電子申請システムの動作環境についてというページ。
ここの確認するボタンを押して判断してもらうのが確実だ。
「推奨のブラウザ…推奨の実行環境が検出されました」と表示されればOK!
あるいは今この記事を見ているインターネットエクスプローラのメニューにある「ツール」から「SunのJAVAコンソール」をクリックしてもいい。バージョン番号が確認できる。(但し5.0は1.5.…、6.0は1.6.…と表示される。)
バージョンが合わない場合はe-Govの解説にしたがって使用可能なJAVAのインストールを!
途中英語のサイトになっちゃうけど、がんばってプログラムダウンロードしてね。
2008年04月23日
これまでのあらすじ・その1
さて、電子申請の仕方を説明する前に、いかにして今日のe-Gov電子申請に至ったかを説明しよう。
昔はみんな紙だった。社会保険も労働保険も所定の用紙に書いて届け出ていた。
社労士がハンコを押し、事業主もハンコを押し、届け出た社会保険事務所や監督署・安定所でハンコを押してもらって控書を返して貰った。
 やがて社保庁が一部で磁気媒体の届書を扱うようになった。磁気媒体、すなわちフロッピーディスク(以下FD)である。
やがて社保庁が一部で磁気媒体の届書を扱うようになった。磁気媒体、すなわちフロッピーディスク(以下FD)である。
資格得失・算定・賞与については磁気媒体届書作成プログラムで作るCSV形式のファイルをFDに保存し提出できる。
しかしハンコだけは変わらず、総括表という紙にそれぞれがハンコを押していた。
磁気媒体で便利になったか?…と問われても、それ程ではなかった。
市販の人事管理ソフトや社労士システムからデータ変換するならばよいが、そうでなければ全て手入力だ。
それならば事前に社会保険事務所から被保険者のデータを入れたFDを送りましょう!
・・・というわけで、ターンアラウンドFDというものが登場する。
これは算定や賞与の時期になると総括表と共に送られてきて、健保番号をパスワード代りにして磁気媒体プログラムに被保険者データを読み込むことができる。
プログラム自体もより使い易くなっていき、FDより丈夫で大容量なMOも使えるようになった。
そして、ここからいよいよ紙もFDもMOも使わずに届け出る手段が登場する。インターネットを使った電子申請だ。
もちろんハンコも使えない。ハンコに代わるものとして電子証明書が必要になった。
さて、詳しくはまた次回へ。
昔はみんな紙だった。社会保険も労働保険も所定の用紙に書いて届け出ていた。
社労士がハンコを押し、事業主もハンコを押し、届け出た社会保険事務所や監督署・安定所でハンコを押してもらって控書を返して貰った。
 やがて社保庁が一部で磁気媒体の届書を扱うようになった。磁気媒体、すなわちフロッピーディスク(以下FD)である。
やがて社保庁が一部で磁気媒体の届書を扱うようになった。磁気媒体、すなわちフロッピーディスク(以下FD)である。資格得失・算定・賞与については磁気媒体届書作成プログラムで作るCSV形式のファイルをFDに保存し提出できる。
しかしハンコだけは変わらず、総括表という紙にそれぞれがハンコを押していた。
磁気媒体で便利になったか?…と問われても、それ程ではなかった。
市販の人事管理ソフトや社労士システムからデータ変換するならばよいが、そうでなければ全て手入力だ。
それならば事前に社会保険事務所から被保険者のデータを入れたFDを送りましょう!
・・・というわけで、ターンアラウンドFDというものが登場する。
これは算定や賞与の時期になると総括表と共に送られてきて、健保番号をパスワード代りにして磁気媒体プログラムに被保険者データを読み込むことができる。
プログラム自体もより使い易くなっていき、FDより丈夫で大容量なMOも使えるようになった。
そして、ここからいよいよ紙もFDもMOも使わずに届け出る手段が登場する。インターネットを使った電子申請だ。
もちろんハンコも使えない。ハンコに代わるものとして電子証明書が必要になった。
さて、詳しくはまた次回へ。












